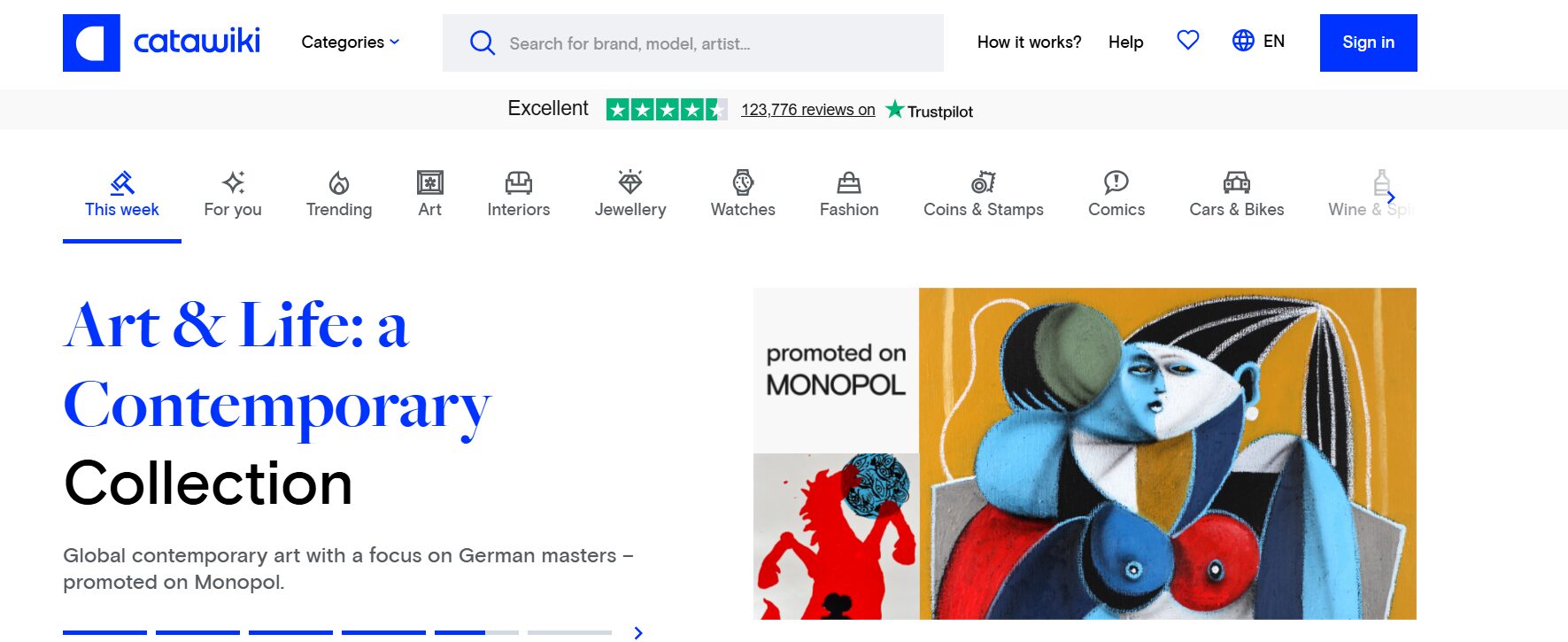※この記事は令和7年2月現在の法令に基づいて作成しています。
こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。
今回は法人において、長年勤めた役員、特に代表取締役が退任して次世代に経営を譲る際に利用できる「役員退職金」について説明します。
役員退職金は、長年の経営実績に報いる意味でも、法人税の節税の意味でも非常に優れた手法です。
それなりに制約はありますが、ほとんどの会社で利用が可能な制度です。
長年、自社を引っ張ってきた社長さんが、次世代に経営を譲る際にはぜひとも利用を検討してもらいたい制度ですので、本記事を読んで契約税理士にご相談してみてください!
なお、他の法人税のブログはこちら。
役員退職金の概要、メリット
 社長
社長佐々木さん、将来のことを考えて、社長である私自身への退職金を予定しておきたいんだが…。
いかんせん、社内で前例がないもので、どういう風なメリットや手続きが必要か教えて欲しい。
役員退職金は、様々なメリットがあります。
特に、次のような目的で支給される方が多いですよ。
- 長年の経営に報いるため
- 所得税の節約
- 法人税の節約
- 株式を次世代に移動させる



様々なメリットがあるんですね!
でも、周りの経営者に聞いたら、意外に役員退職金をもらっていない会長さんもいたりして…
制約も多いんですかね!?
役員退職金は非常に便利で、かつ、社長さんの長年の苦労に報いることのできる制度です。
しかし、同時に手続き上の制約が多少ありますし、会社独自で実行するには少しハードルが高いです。
契約している税理士さんと共同で行う方が安全ですし、役員の退職は登記も必要になりますので司法書士さんの力も借りる必要があります。
でも、そういったハードルを乗り越えてでもやる価値のあるものですよ。
役員退職金のメリット



もう、単刀直入に役員退職金のメリットから教えてください!
その方が社長も、社長の家族もやる気が出ますから。
ではまず、メリットから記載していきます。
①長年の経営に報いる
いきなり、気持ちの部分から始めます。
経営者、とくに中小企業の社長は長年、会社を支えて、同時に、従業員の生活を守ってきました。
それに対し、十分な役員報酬をもらっている場合もありますが、人によっては自分の報酬を削って従業員の給料に充てている人もいます。
いずれにしても、税理士として、また、一経営者として、「社長は在籍年数に応じた退職金をもらうべき、また、もらって欲しい」というのが私個人の意見です。
その金額の算定方法は「所得税法上の退職所得控除の算定」、「法人税法上の役員退職金の算定」の2パターンありますし、それにかかわらずに支給することもできます。
いずれにしても、次世代の経営者が先代経営者の退職の際に敬意を示す方法としてはマストと思っております。
②所得税の節税



あっ、これは社長も言っていました。
自分で調べながら「退職金をもらった方が税金が少なさそうだな…」とか。
役員退職金をお勧めする理由の一つが「退職金をもらう本人が負担する所得税が少なくなる」ということです。
役員報酬で延々ともらい続けるよりも、はるかに低い税金で済みます。
社会保険料の負担も考えたら、その差額はすさまじく変わります。
まず、所得税法上の退職所得の計算についてみてみましょう。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)



文字で見ると難しいですね…。
文字で見ると難しく感じますが、ポイントは二つ。
- 「退職所得控除」
- 1 / 2



「退職所得控除」は名前は聞いたことくらいありますが…。
ちゃんとした中身は知りませんね。
退職所得控除は、名前はそれなりに知られていますし、「なんか優遇されている」くらいの認識は世間でありますが、明確な計算式を知っている人は少ないです。
計算式は次のようになっています。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
難しく見えるかもしれませんが、とりあえず「給与でもらうよりはるかに控除されて税金がおトク」と考えればよいです。
参考までに、ある年に
①役員報酬で2,400万円(200万円×12月)もらうケース
②退職金で2,400万円(勤続30年)もらうケースで計算してみます。
※給与以外の所得なし、基礎控除を含めた所得控除を無視
①役員報酬で2,400万円のケース
2,400万円 ー 195万円(給与所得控除) = 2,205万円
2,205万円 × 40% ー 2,796,000 = 6,024,000円
退職金で2,400万円もらうケース
2,400万円 ー (800万円 + 70万円 × 10年) = 900万円
900万円 × 1/2 = 450万円
4,500,000 × 20% ー 427,500 = 472,500円



納める税金の額が…
600万円と47万円で、500万円以上違いますね…。
このくらい、平気で変わってきます。
社会保険料の負担も考えれば、さらに節税される可能性があります。
理由は退職金が「退職所得」に該当すれば、退職所得控除と1/2の計算にはまり、大幅に税金が削られるからです。
また、退職所得が社会保険料の算定基礎での計算に入りません。
(つまり、退職金に社会保険料はかかりません)
それだけで、役員報酬で毎月もらうよりもはるかに多い金額を節税できます。
このために経営者としての最後に「役員退職金」をもらう価値はあるというものです。
③法人税の節税



もらう人の税金だけでなく、法人の税金にも影響があるんですか?
役員退職金により、法人の税金(法人税、地方法人税、地方税)にも影響します。
例えば、毎年400万円ほどの利益(=所得)を生み出している中小企業があるとします。
※利益=所得の法人で、特別控除などはないと仮定。
地方税均等割は無視します。
だいたい、毎年の法人税等は100万円(法人税72万円、地方法人税7.3万円、事業税14万円、地方税7万円)ほど納めているとしましょう。
それが、ある年に役員退職金3,000万円を計上します。
すると、利益(=所得)は 400万円 - 3,000万円 = ▲2,600万円 まで減少、というか赤字になります。
であれば、法人税等は0円になります。
先ほどの例(法人税等100万円)であれば、予定納税を50万円しているでしょうから、実際には確定申告後に50万円還付です。



簡潔に言うと…
法人税が100万円納税から0円になる…
そして、予定納税していれば、その金額がすべて戻ってくるということでしょうか。
その通りです。
そして、▲2,600万円の赤字は、「10年間繰越が可能」です。
毎年、400万円の利益が見込める会社であれば、6年間は法人税が発生しません。
もしくは、以前に解説した「欠損金の繰戻還付」と合わせて行う方法もあります。





それって、かなりすごい節税なんじゃ…。
かなりすごい節税方法だと思います。
ただ、当然ながら法人税法上の損金に計上するためには「役員在任期間」「地位(代表取締役or専務、平取締役?)」「功績倍率」などの要素が絡みます。
この点は、また別記事にしたいと思いますが、契約税理士さんと協同して行うことをお勧めします。
④株式を次世代に移動させる
そして、最後に事業承継を考えたときに、相続税対策として早めの株式承継を考えることがあります。
その際に、会社に利益が溜まっていると、株式価値も大きくなってきます。
そこで、役員退職金により一時的に大きく財務を悪化(純資産を減少)させ、株式価値を低くしたタイミングで親族に株式継承させる方法がよく使われます。
定番の方法ですが、被相続人(社長)の資産が大きい場合で相続税が多額になるケースではかなりの効果を発揮します。
この相続対策まで考慮すると、確実に資産税に強い税理士と協同した方がよいです。
(というか、協同しないと無理です)
役員退職金のデメリット



なるほど、やはりメリットが多いな。
でも、デメリットも当然にあるんだろう?
メリットがあれば、デメリットがあるのも世の常です。
便利な役員退職金ですが、そのデメリットも踏まえて使う必要があります。
①退職する必要がある
当たり前のことを言っていますが、実際に退職する必要があります。
なぜ、この「当たり前」のことをわざわざ書くかと言うと、「退職金はもらい、登記簿上も役員から削除された。しかし、相変わらず次期社長と一緒に重要な決断をし、銀行借入の際に同席している」ケースがあるからです。



「退職」って、登記簿から削除されて、組織表からいなくなれば「退職」なんじゃないんですか?
税法は「実態」を重視します。
そして、「実態」というのは、「会社の経営で本当はどうだったか」ということです。
つまり、「株主総会で退職の議決を得て」「登記簿から削除された」という形式はあったとしても、その後で実際に次世代の社長に成り代わって、もしくは一緒に重要な決断をしている、債権者交渉をしているようでは「退職」とは言えません。
つまり、「退職」というのは、「実際に会社の重要事項に関与しない」必要があります。
もちろん、現場の技術者として引き続き働かれるのは問題ありません。
しかし、「社長」でなければできない仕事を引き続きするのは「退職」とは言えないので注意です。
税務調査を考慮すると、「実際に退職し、社長の仕事をしていないか」については、従業員や金融機関に聞き込みされる可能性があります。
この点、自分(会社側)では、判断がつかない場合が多いので、どの程度の関与までなら許されるか、契約税理士に相談することをお勧めします。
②組織変更
昔ながらの会社でよくある事項です。
社長が退任すると、「取締役の定足数である3人に不足するので厳しい…」ということです。
これは、「取締役会設置会社」と定款で決めている会社でよく起こる問題です。
社長(取締役)が退任すると、ギリギリ3人の取締役で運営していたが、3人に足りなくなる、という場合に問題が生じます。
このため、社長が在任し続けるケースもあります。
しかし、中小企業に「取締役会」が必要かどうか、銀行融資や親会社、関連会社対応でそこまで求められているかは確認した方が良いです。
社長の退職を機会に、「取締役会非設置会社」、つまり取締役一人で成り立つ会社に変更してはいかがでしょう?
監査役も不要になりますし、取締役退任、監査役退任の際に引継ぎを考える必要がなくなります。
変更登記で司法書士さんに頼むと15万円程度かかりますが、「役員退職金」による節税効果を考慮するとプラスのはずです。
将来的に、次世代(息子の代など)に、取締役、監査役の選任で困らないようにと考えればいいタイミングかもしれません。
③金額設定にコツがある
最後に、退職金の設定には少しコツが必要です。
大まかに、所得税法上のアミと法人税法上の制約があります。
所得税法上のアミは「退職所得控除の上限」です。
つまり、そこを超えたら所得税が発生するということ。
逆に言えば、所得税を支払うならアミを超えても問題ありません。
法人税法上の制約は「損金算入限度額」という、会社の経費として法人税法上で認められるかどうかの制約です。
こちらは、会社の歴史、社長の貢献度、在任年数、最終報酬月額で大幅に変わります。
税務調査で否認されると、会社の法人税に多額の影響が出るので、検討が必要な部分です。
(最終報酬月額による算式を使うことが標準ですが、金額の多寡や状況にもよります。
当事務所では、最終報酬月額での計算もしますが、最終的には過去の社長としての寄与度なども合わせて検討します。)
④形式が必要
役員退職金は「役員が退職し、長年の会社への功労に対して退職金を支給する」というものです。
役員退職金の支給にあたっては、最低限の形式は必要です。
具体的には、
- 株主総会での決定
- 役員退職金の決定過程
- 退職金の受給に関する申告書の用意
この程度の用意は必要です。
通常は、契約税理士がいれば用意してくれるでしょう。
契約税理士に「何を、いつまでに、どうすればよいのか?」を聞いてください。
すると、「〇月くらいまでに当事務所で株主総会議事録や計算方法、退職金の受給に関する申告書など用意いたします」と回答があると思います。
この点、気になる部分は詳しく聞きましょう。
金額も大きいですし、数十年に一度の事象なので、質問するのに遠慮は不要です。
役員退職金のまとめ



なるほどなぁ…。
参考になったよ、佐々木さん。
特に、うちの会社は代理店で、取引元の意向で監査役設置会社にしている(取締役会設置会社)にしているから、私が退任すると役員選定が必要だな…。
いや、この際、監査役なしにしてもいいかも…。
今回、この役員退職金の話を記載したのは理由があります。
ちょうど、当事務所の顧問先で、数十年間優良に利益を計上し、法人税を納付(年で100万円以上)してきた企業の税務契約に令和6年度で携わらせていただきました。
会長はすでに80歳近く、息子さんに社長を譲って、自由に現場で技術者として仕事をしています。
ただ、取締役会設置会社であるため、登記上で取締役を続けなければいけない状態でした。
当事務所としては、すぐに「役員退職金の設定と取締役会設置会社の廃止」をすれば、法人税の支払いも数年間はなくなり、役員選任で悩む必要もないのになぁ、と思って提案させていただいた次第です。
結果としては、すぐに登記変更、会長の退職金の支給決定、退職金による赤字による繰戻還付により120万円程度の節税につながりました。
また、取締役及び監査役の選定にも悩まずに済むようになりました。
(当事務所に変わる前の税理士先生とは、年1回の面談だったようで、決算を組むのみ、そういった細かい話はできなかったそうです)
これは成功例ですが、こういうケースもあるということを頭に入れておいて欲しいと思います。
こういうケースで少しでも会社にトクになるようにアドバイスできるのが税理士の特権と思っております。
もちろん、脱税はダメですが、法律にのっとった節税はおおいに利用すべきです!
役員退職金について相談したい方は気軽にどうぞ。