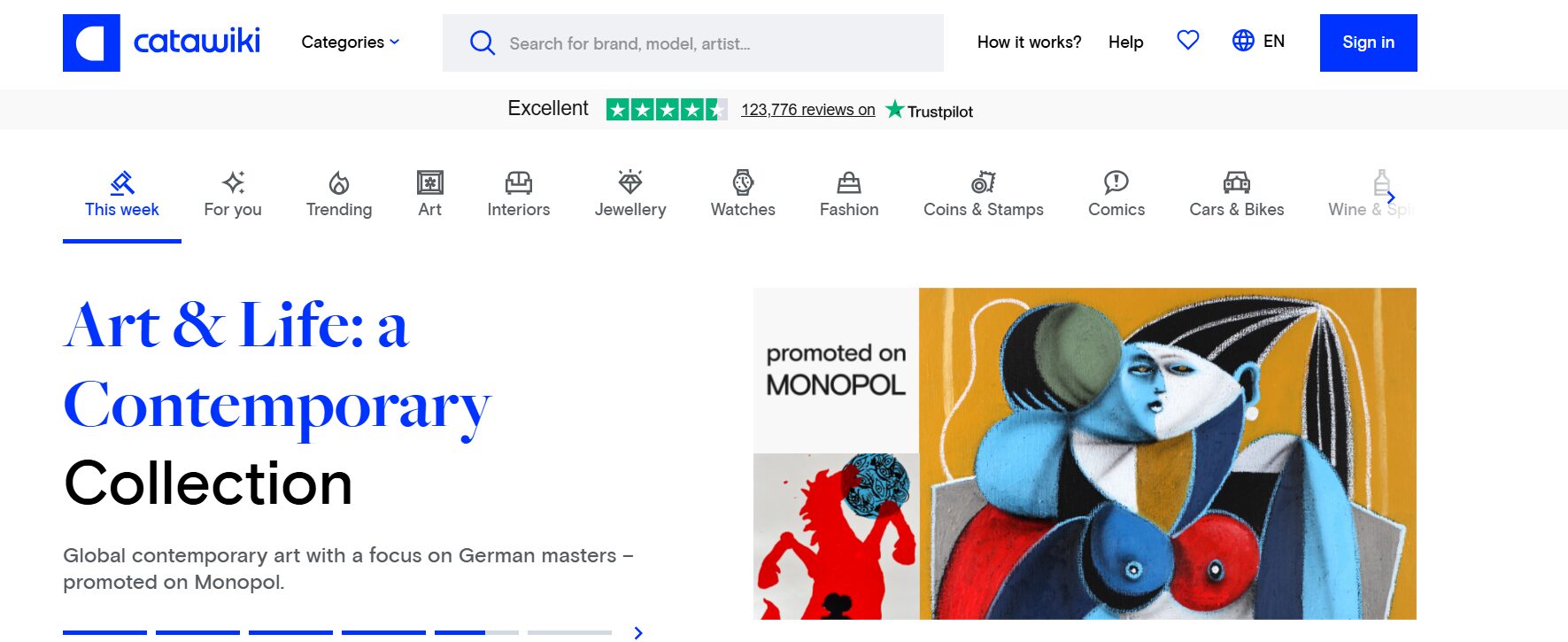※この記事は令和7年3月現在の法令に基づいて作成しています。
こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。
今回は、個人が土地や建物を貸して収入をあげる際の「不動産所得と青色申告」について解説します。
不動産所得では「青色か白色か」、「事業的規模か業務的規模か」という判断が必要となります。
この点をしっかり判断していないと税務上でリスクを負うことになります。
この点解説していきます。
※なお、この記事では、「事業的規模に至らない規模の不動産の貸付」を「業務的規模」と呼ぶこととします。
なお、過去の所得税のカテゴリのブログはコチラ。
不動産所得と青色申告特別控除
 スタッフさん
スタッフさん佐々木先生。
私、将来はFIREして不動産の収入で生きていく予定です。
30代後半にはFIREしたいです。
不動産で儲かった時の税金について教えてください。
確定申告時期には、不動産収入のある会社役員さん、大家さんなど個人の確定申告で税理士事務所は忙しくなります。
不動産収入は個人の確定申告上、「不動産所得」として給与所得、事業所得などと区別されます。
その中でも、個人の確定申告をする上で「10万円~65万円」を控除できる「青色申告特別控除」の制度は不動産所得においては独特の判断基準を持っています。
次の判断基準で青色申告特別控除が変わりますので、参考にされてください。
1.不動産所得の事業的規模と業務的規模
まず、不動産所得、つまり賃貸アパートやマンションの経営を行ううえで、それが「事業的規模」なのか「業務的規模」なのかの判断が必要です。



「事業的規模」なのか「業務的規模」なのかで何が変わるんですか?
けっこう大きな違いがあります。
主に次の点が変わりますね。
- 青色申告特別控除の金額
- 事業専従者給与の可否
- 除却などの資産損失の赤字を他の所得と相殺できるか、または繰越できるか
- 賃貸料収入の貸倒を進行年度(現時点の年度)で処理できるかどうか
今回は上記の細かな解説は省略しますが、実際に不動産経営をすると、違いを感じる部分も多いでしょう。
とくに、「青色申告特別控除の金額」と「事業専従者給与の可否」は毎年違いを感じる部分です。
そして、「事業的規模」と「業務的規模」の判断に加え「青色申告」と「白色申告」の違いもあるため、なお複雑です。
不動産所得での青色申告特別控除について
①青色申告特別控除65万円を取ることができる場合
まず、当然ながら青色申告特別控除の最大金額65万円を取ることができる方が良いに決まっています。
青色申告特別控除で65万円を控除できれば、所得税と住民税で10万円以上変わってきます。
国保に入っている方の場合には、国保の金額にも影響しますので、大きいです。
その判断基準は次のとおりです。
不動産の貸付けが事業として行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
国税庁 タックスアンサー No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分
簡潔に言うと、「アパート・マンションについては10室、一戸建てについては5棟」以上貸していれば、それは「事業的規模」とみなされて65万円の青色申告特別控除を取ることが可能となります。
もちろん、これ以外にも「複式簿記で経理して貸借対照表を整備し、電子申告を行うこと」が条件となります。
【参考】
貸付が駐車場の場合:50台分の貸付で事業的規模となります(5台分でアパート1室に相当)
土地の貸付:土地5か所の貸付をアパート1室と判断する考えがあります。
明確な判断基準はありませんので、実態(地代や管理費の程度)を見て判断となります。
②青色申告特別控除10万円となる場合
①の条件(アパート・マンションについては10室、一戸建てについては5棟)に満たない場合は、業務的規模となり、青色申告特別控除の金額は10万円となります。
この場合、青色申告特別控除は10万円の控除となりますが、メリットもあります。
それは、「単式簿記で記帳すればよく、貸借対照表は不要。また、紙で税務署に提出してOK」というところです。
家計簿の延長でアパートなどの賃料を毎月ノートに記録し、経費も各レシートなどを取って置き、ノートに記録。
1年のまとめを紙の決算書に記載、確定申告書に転記して税務署に提出してOKです。
これなら、税理士費用がかからないというメリットもありますね。
(確定申告書を自分で作れるという前提はありますが…)
2.不動産所得の規模の違いのまとめ



何だか混乱してきました…。
結局、5棟10室で何ができるんでしたっけ?
不動産所得は切り口が多い(「青色申告」か「白色申告」か、「事業的規模」か「業務的規模」か)ので、混乱しますよね。
簡単にまとめていきます。
①青色申告特別控除について
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事業的規模 | 65万円 or 55万円 ※10万円でもOK | なし |
| 業務的規模 | 10万円 |



青色申告特別控除の有無の違いは分かりやすいですね。
青色ですと規模で控除額が違う。
白色は控除なし、ということですね。
②事業専従者給与について
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事業的規模 | 青色事業専従者給与が可能 ※事前届出が必要 | 事業専従者給与が可能 ※届出不要 |
| 業務的規模 | 利用不可 | |



なるほど~。
家族に給与を出すためには「事業的規模」じゃないとダメなんですね。
あとは、青色なら届出をして給与額を設定できるんですね。
③赤字の処理
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事業的規模 | 他の所得との赤字の相殺が可能。 赤字の翌年以降3年間の繰越可能。 ※(損益通算で他の所得との相殺後に赤字が残った場合) | 他の所得との赤字の相殺が可能。 赤字の繰越は不可能。 |
| 業務的規模 |



赤字の相殺はいずれの場合も可能なんですね。
青色なら規模にかかわらず、赤字を繰り越せると。
④貸倒の処理
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事業的規模 | 貸倒損失について、貸倒発生時の経費として処理可能。 | |
| 業務的規模 | 収入計上年分まで遡って申告書を修正。 更正の請求が可能。 | |



なんか…。
よく分かりません??
事業的規模の「貸倒発生時の経費として処理」は分かりますが、業務的規模の過去に遡ってがなんかよく分かりませんね…。
前提として、不動産収入は原則として「契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日」という風に、「実際の支払いがなくとも収入計上する」という原則があります。
●国税庁 タックスアンサー No.1376 不動産所得の収入計上時期
そうすると、現金収入はないのに、確定申告上では、収入として計上して所得税を支払うことになります。
それが、数年後に賃借人と連絡が取れないなどで貸倒れとなるとどうなるか、という話です。
普通に考えれば、「貸倒れとした年分」で経費処理すればいいじゃない、と思いますが、業務的規模の場合には「過去に遡って申告書を修正し、更正の請求してください」ということです。



そんな面倒なことする人が世の中にいるんですか…?
私は税理士という立場上、上記のとおりにアドバイスし、依頼されれば資料を添えて更正の請求をします。
でも、税理士に依頼せずに自己申告されている方が上記のようにしているかは…してないでしょうね。
税務調査で見つかって指摘されたら、貸倒発生年度は修正申告、収入計上年度は更正の請求ということになりますが、個人に対してそこまで調査で指摘するかは何ともいえないところです。
不動産所得と青色申告のまとめ
結局、不動産所得の青色申告を記事にするためには「事業的規模」と「業務的規模」の話になりますね。
そうすると、「青色申告」「白色申告」「事業的規模」「業務的規模」の4つの視点での切り口になります。



ありがとうございます。
不動産は税金関係も難しい、ということがよく分かりました。
早めに「5棟10室」にしたいなぁ。
なお、「5棟10室」はあくまで目安です。
「5棟10室」に達していなくとも、「社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうか」によって考えることが原則です。
例えば、1室20万円の高級賃貸マンションを5室貸していれば、それだけで月に100万円の収入。
年間ですと1,200万円ほど収入となります。
収入金額だけで測るものではありませんが、投資によりリスクを背負い、生活が成り立つに十分な収入があれば「事業的規模」となる可能性は十分にあります。
この点、事前に税務署に確認する、税理士にそうだんしてみるなどしてみてください。
不動産経営の税務処理について相談、依頼されたい方は気軽にご連絡ください。