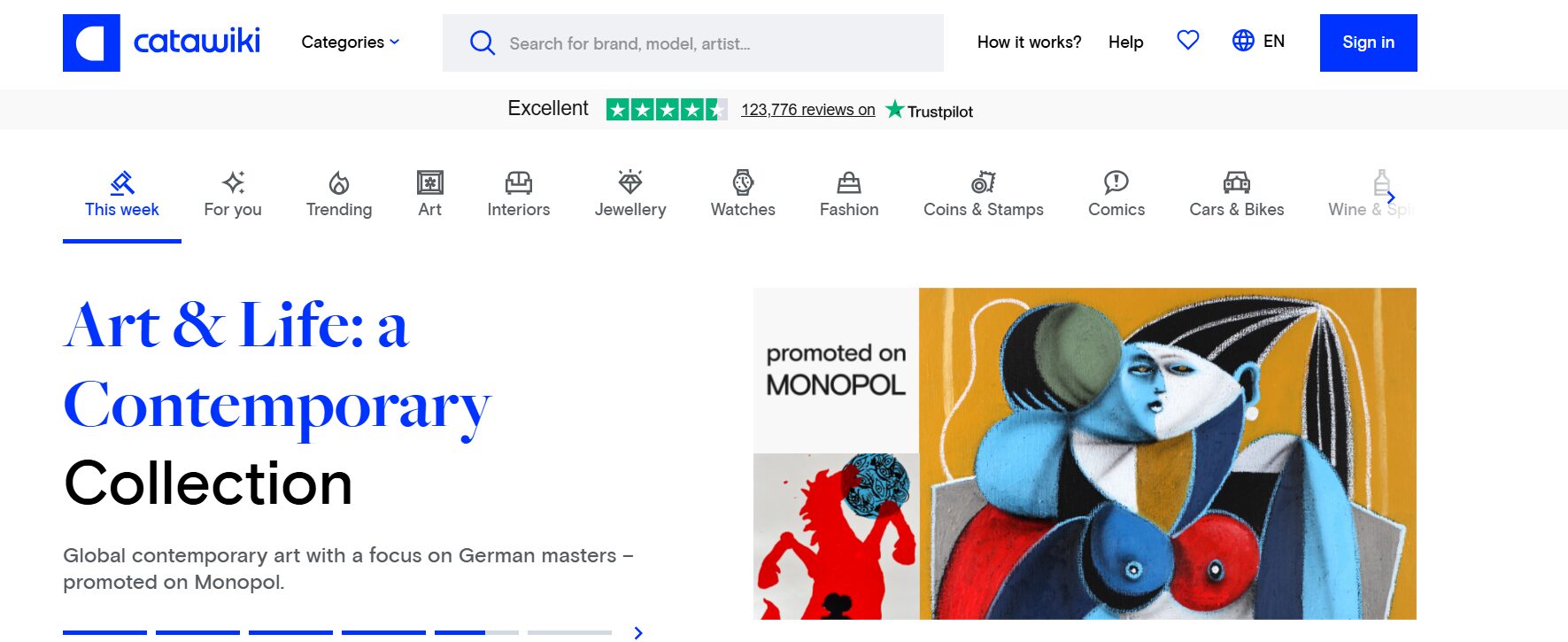※この記事は令和7年7月現在の法令に基づいて作成しています。
こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。
今回は相続の際に相続財産からマイナスするもの、つまり、被相続人(亡くなった方)の債務について解説します。
相続財産はプラスのものだけでなく、マイナスのものもありますよ、そして、それは申告の際にきっちりと引くことで相続税の軽減につながりますよ、という話です。
なお、相続の他のテーマはこちらから。


相続税の計算上の債務(マイナス)
 社長
社長佐々木さん…
今回はちょっと、相続税での計算でマイナスになるものを教えてもらえるかな?
プラスの財産もあるなら、マイナスの財産も当然にあるんだろう?
相続税の計算はプラスの財産をかき集め(みなし相続財産、保険金などを含む)、非課税となる部分を控除し、さらにそこからマイナスの財産を引いて計算します。
被相続人(亡くなった方)の見た目の財産は多くても、調べてみたら遺産総額はそうでもなかった、というケースもありえます。
(とくに、会社経営者や個人事業主ではありえます)
- 被相続人の借金、借入金
- 求償が不可能な保証債務
- 未払金
- 葬式費用など
ここらへん、ザっと国税庁でもまとめています。
国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務
この記事では、もう少し詳しく見ていきます。
①被相続人の借金、借入金



「借金」と「借入金」って何か違うんですか?
あ、ニュアンスが違うだけなので、あまり気にしないでください。
両方とも「お金を借りること」です。
ニュアンスとして「借金は個人が生活費のために借りる」、「借入金は事業用で借りる」くらいのニュアンスでしょうか。
そして、「借金」と「借入金」の両方とも、遺産総額から差し引くことができます。
ただ、ポイントがあります。
- 被相続人の死亡時点での残高が対象
- 未払いの利息も対象
「借金」と「借入金」のうち、「借金」つまり個人間のやり取りは少し注意が必要です。
実際に被相続人とだれか他人の間でお金のやり取りがあったとしても、「契約書」などの明文化された書類がないと認められないことがあります。
また、返済実績が一切なく、数年放置の場合には贈与してもらっているものでないか、という疑いも起こります。
ここら辺、実態をよく調べずに安易に債務控除してしまうと、税務調査で否認のリスクもあります。
これに対し、金融機関との「借入金」については契約書や返済予定表もあるでしょうから、間違いがありませんね。
②債務保証、連帯債務の扱いは?



債務保証、連帯債務…
すいません、単語は知っていますが、どう違うんでしたっけ?
簡単に説明します。
債務保証:債務者が債務を履行しない場合に保証人代わりに債務を支払いますよ、という契約
連帯債務:一つの債務を複数人で背負う契約
債務保証は、保証人よりも先に債務者が支払いをし、債務者が支払いなどできない際に保証人に支払い義務が降りかかります。
よって、保証人であるというだけではまだ債務を負っているわけではありません。
したがって、債務保証の状態は原則として、遺産総額からの控除はできません。
ただ、保証人が支払うことができなくなると、保証人が支払う状態にレベルアップします。
そして、保証人が代わりに支払うと、今度は保証人から債務者に対して「求償権」を持つ状態に移行します。
この状態でも「確実に債務者が保証人に弁済できない」ことが確実な状態にならないと債務控除できません。
うーん、保証制度はなかなかに厳しいですね…。
参考:国税庁 タックスアンサー No.4126 相続財産から控除できる債務
連帯債務は、直接に債務者となっている状態です。
ただ、同時に債務を負っている人が複数いるだけの状態。
よくあるのは、住宅ローンで夫婦でローンを負う、連帯債務の状態となる状態ですね。
連帯債務は、直接に債務者となっているので、条件が合えばには遺産総額からの控除ができます。
(各自の債務額が明確になっている、など)
保証と連帯債務は少し難しいので、よく分からない場合には税理士さんに相談して方がよいですね。
③未払金



会社であれば未払金は日常的にありますが…。
個人の場合は未払金ってどんなものがあるんですか?
個人であっても未払金はけっこうあります。
よくあるものを例示しておきますね。
A.所得税、消費税、住民税
まず、税関係です。
個人事業主、不動産オーナーなどの場合、1月1日~亡くなる日までは所得が発生しています。
亡くなった後は、死亡日の翌日から4ヶ月以内に「準確定申告」というものをして、所得税を確定させる必要があります。
この準確定申告により確定した所得税(消費税がある場合は消費税も)は債務控除として遺産総額から引きます。
また、住民税で被相続人が納めていないものがある場合、債務控除の対象となります。
B.固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課せられる税金です。
ただ、実際の支払いはその年の4月以降になります。
したがって、亡くなった時点で未払いの固定資産税がある場合にはその分を控除できます。
なお、固定資産税は、年4回に分割して支払いますが、1年分の未納分すべてを債務控除できます。
例えば、被相続人が3月に亡くなった場合、4月、7月、12月、翌年2月に納期限が到来する分のすべてが債務控除の対象となります。
C.未払いの医療費
被相続人が亡くなる直前まで入院されていた場合には、医療費が未払いとなっているはずです。
その未払いの医療費は債務控除の対象です。
D.未払いの公共料金、携帯電話料
被相続人が亡くなる直前までの自宅にかかる公共料金(電気、ガス、水道)や被相続人の携帯電話料も債務控除の対象です。
ただし、死亡日までのものが対象です。
E.個人的な未払金
上記の他、被相続人が何かを購入し、その代金がまだ支払われていなかった場合には、その未払いの代金も債務控除の対象です。
あまりないと思いますが、私(当事務所代表)の実父が実際にこの未払いの代金を残して亡くなっています。



何の料金だったんですか?
うちの父は昔、小説家になりたかったようです。
それも歴史小説家。
人生の最後、亡くなる1年前から歴史小説を書いていましたが、ガンで余命が分かると書き溜めた原作を本にしたかったみたいで、いわゆる歴史小説の自費発行を出版社に依頼したんですね。
そして、そのまま完成版を見ることなく天寿を全うしました。
ということで、出版社への製本代金(300万円くらいだったかな)が未払金として残った形ですね。
なお、父の最後の願いだったので、完成した歴史小説は父の血縁、友人に配りました。
当然、私も1冊保管しています。
④葬式関係費用



葬式は必須ですもんね。
金額も100万円以上しますし。
ただ、香典とかありますが、どうなるんですか?
葬式関係の費用は、被相続人の債務ではありませんが、債務控除可能です。
そして、けっこう細かいです。
まずは、根拠を確認。
国税庁 タックスアンサー No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
債務控除できる葬儀関係費用を参考列記します。
- 告別式、お通夜のために葬儀会社に支払った費用
- 告別式、お通夜関係の飲食費用
- お坊さんへのお布施、戒名料など
- 死亡診断書の発行費用
- 火葬料、埋葬料
なお、香典をもらった場合でも上記の費用からマイナスする必要はありません。
その代わり、香典返しについても債務にはなりません。



香典も香典返しも相続税のうえでは気にしなくていいんですね。
次に、葬式関係で債務控除の対象にならないものも挙げておきます。
- 香典返し
- 初七日、四十九日法要の費用
- 墓石、位牌の購入費
初七日法要を告別式を同日に行うことも増えていると思いますが、その葬儀会社の請求書に初七日法要と告別式の区分がなかったらどうなるんだ?みたいなマニアックな論点もあります。
葬儀関係費用については、債務控除に入れられる、入れられないが細かいです。
分からない部分がありましたら、税務無料相談など市町村で開催していることがありますので、相談した方がよいです。
相続税の債務控除のまとめ



なるほど…。
佐々木さん、実は若いころに連帯保証した債務があるんだが…。
後でちょっと相談に乗ってくれないかね?
身内と言えども、その人の一生をすべて知っているわけではありません。
「実は借金があった」「実は連帯保証人になっていた」「実は山奥に土地を持っていた」など、亡くなってから判明する事実もけっこうあります。
その中で、相続財産となるもの、相続財産から引ける債務控除となるものなど、相続人では見分けが付かないものもケースによってはあります。
そんな時には、税理士に相談された方が良いでしょう。
市町村の無料税務相談などもありますので、普段からそういったところに行ってみるのも税務へのハードルを下げるきっかけとなります。
相続で困った際は遠慮なくご相談ください