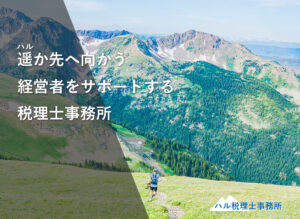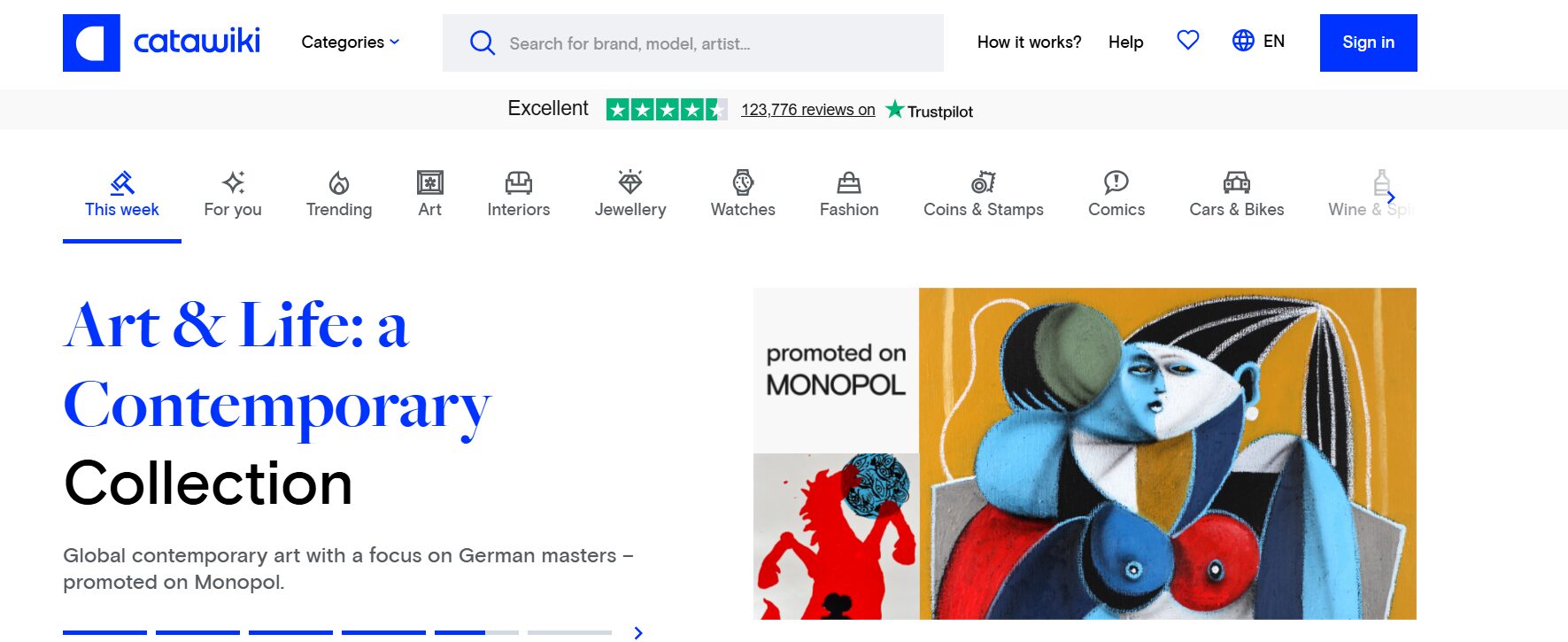こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。
今回は「会社は何のために」という答えのない問いについてです。
あくまで、当事務所の考え方を示すとともに、当事務所のモットー「遥か先へ向かう、経営者をサポートする税理士事務所」の意味も書いておきます。
なお、経営関係ブログは他にもあります。

会社は何のためにあるの?
 2代目(予定)
2代目(予定)今回は哲学的な問いですね…。
「会社は何のためにあるのか?」これは、答えがない問いですね。
経営書では「株主、経営者、従業員、ステークスホルダー全般」いろいろな書かれ方がされています。
しかし、当事務所の考え方はシンプルです。
1.会社は「経営者のため」



シンプルな答えですね。
「経営者」のためなんですね。
あくまで、当事務所の考え方です。
当事務所のモットー「遥か先へ向かう、経営者をサポートする税理士事務所」というものは、私が開業するときに考えたものですが、目的語を「経営者」にしました。
これは、当事務所の姿勢を表す言葉として適当だと思ったからです。
「経営者」を目的語、主体とする考え方は、当事務所の次の理念に基づいています。
ハル税理士事務所は、「経営者」の人生を末永くサポートします。
経営者は、「会社」というものを興し、自分の責任で取引先と交渉、取引し、従業員を雇用してその暮らしを確保し、資金繰りのために自分の財産を担保として金融機関に差し出し、取引先とトラブルがあった際には(従業員のミスであっても)自分で責任を取ります。
それだけ大変な役目を負う「経営者」をサポートするのが当事務所の使命です。
場合によっては、「会社」よりも「経営者」を優先する提案もためらいません。
2.「経営者のため」の理由



こう見ると、経営者は責任が多いですね…。
経営者は責任だらけですよ。
自分も開業したからこそ思うことが多いですが、経営者は自分の事業のすべてに責任を負います。
取引、従業員の動き、資金繰り、外注さんの仕事にも尻ぬぐいが必要です。
そのような経営者の味方はだれか!?
家族、従業員、金融機関、取引際…??
上に挙げた人たちがそうであり、そうでないようであり…経営者というのは「自分の事業を理解し、味方であってくれる人」が少ない職業と思います。



うむ…。
その通りだな。
そのような事業全体、バックオフィス、プライベートの部分まで把握して味方になってくれる人は少ないでしょう。
では、税理士である自分は報酬をもらって仕事をいただいています。
報酬うんぬんもありますが、それ以前に、いつでも経営者の味方でいたい、そう思っています。
味方のいない経営者は、ときに変な方向に走ることがあります。
投資・保険を勧める金融機関・保険会社の営業さんに味方のふりをされ、言いなりになるケースもあります。
(本当に相手のためを思ってくれる金融機関、保険会社さんもいますが、そうでない方も一定数いらっしゃいますので…)



私のもとにも、よく投資の営業さんが来るが、佐々木さんと同席してもらっているからほとんど断っているなぁ。
必ずしも断る必要はありませんが、客観的に見ることは大事です。
当事務所(私)の視点は常に「経営者」の役に立つか否か、です。
投資を進める金融機関・保険会社の視点が「会社のため」であれば、そこは一言社長さんにリスクを伝えさせてもらっています(養老保険なんかはまったくダメ、とか言っています。中退共もリスクを説明してややマイナスに伝えているくらいです)。
よく、「会社の節税になります」と言って保険、外国債券、福利厚生サービスなどを勧める方もいらっしゃいます。
それ自体は別に否定しませんが、「会社の節税」にはなっても「社長の利益」になるかは別問題です。
その投資をするくらいでしたら、「税理士の私と一緒に古町(新潟市内の歓楽街)に言って、プロの接待(専門の女性の方)を研究してきますか?すぐに接待交際費で損金になりますよ(笑)」なんて言っています。



うむ…。
それも、本当に役立つ営業の神髄…。
佐々木さん、また古町の××××さんへ



社長!
3.「会社」と「経営者」の違い
①「会社の利益」と「経営者の利益」に乖離が起きやすいケース



うん…。
熱量は伝わりましたが、「会社のため」はイコール「経営者のため」という気がしますが、違いますかね?
ここも当事務所の考え方となりますし、同時に税理士としていろんなケースを見てきた経験でもありますが、「会社の利益」と「経営者の利益」は一致しないケースがあります。
それは、明確に次のケースです。
会社と経営者の利益が一致しないケース
⇒ 従業員を抱え、かつ、「会社の経営がうまくいっていないとき」
会社の経営がうまくいき、売上、利益が伸びているときは経営者の報酬も上がります。
また、その残余利益を「従業員に還元」できます。
したがって、会社が右肩上がりの時にはさほど「会社の利益」「経営者の利益」に乖離が起きません。
もしくは、乖離があったとしても気付きません。
問題は、会社の経営が右肩下がりのケースです。
②どんなことが起きる?
端的に言うと、「従業員の利益」と「経営者の利益」がぶつかることが多いです。
会社の経営が右肩下がりの場合でも、従業員がいない、もしくは、家族だけの場合には自分たちの報酬・給料を下げて何とか凌げます。
しかし他人である従業員を雇用している場合には「給料を下げて凌ぐ」ということはできません。
労働法により給料の減額は制限されていますし、そもそも、そのように従業員の給料を減額すれば退職される可能性もあり、さらには「あの会社は倒産のおそれあり」とうわさが流れる可能性もあります。
地方では、うわさが広まる速度は音速レベルです。
うかつなことをすれば、あっと言う間に変な噂が流れます。



これは…
たしかに分かります。
うちの地域でも変な噂ほどあっという間に広がります…。
まぁ、噂の話は置いておいて、経営が傾いても、従業員の給料は削ることはできません。
責任感の強い経営者なら、なおさら「自分の給料を削ってでも」「金融機関に土下座してでも従業員の給料分を…」という思考にとらわれます。
果たしてそれが、「経営者」のためになっているかはケースバイケースと思っています。
③乖離を引き起こす原因



従業員との利益の取り合いみたいなところが多いんですね。
その他にも「会社」と「経営者」で利益の取り合いみたいになるところってありますか?
私の方で気を付けているケースは次のような部分ですね。
- 全社員対象の養老保険
- 中退共
- 福利厚生サービス
- 給与のベアアップ
- 給与・社保関係の制度を従業員有利に変えること



佐々木先生…
なんか従業員を目の敵にする人みたいになってますよ(笑)
私も書いていて、「従業員に優しくない、鬼のような人だな…」と思いました(笑)。
もちろん、会社の業績が右肩上がりでその傾向が続きそうなときに福利厚生を強くする、賞与を多く出すなど、無理しない範囲のアドバイスはきちんとしますよ。
ただ、会社には必ず「上向き、下向き」の流れがありますので、その際に維持できない制度、待遇はやめた方が良いと思っているのです。
その他にも、大きくお金が動く際には、社長個人へのダメージも想定しながら一緒にシミュレーションするようにしています。
- 大きな設備投資(補助金の有無も合わせて)
- 人材獲得(助成金の有無も合わせて)
- 新規事業進出
物事には良い側面と悪い側面があるのと同じで、「会社」にとって良い面と「経営者」にとって良い面が一致していないこともありますから。
4.ハル税理士事務所の具体的な対応



なるほど…。
「会社の利益」「経営者の利益」が乖離することは、分かりました。
でも、その場合に具体的に佐々木先生はどのような提案をするんですか?
状況にもよりますが、基本的には経営者の生活、人生が成り立つ方向のアドバイスを優先します。
具体例を挙げれば、次のような相談が来ることがあります。
- 前期から景気が良く、今期もかなりの利益が見込めそうです。
決算賞与にするか、ベースアップか、その両方か迷っていますが、先生はどう思います? -
1.決算賞与は良いと思います。
従業員さんの頑張りを還元できますし、所得拡大促進税制と言って減税になる措置もありますし。
2.ベースアップは検討が必要です。
一度上げれば、下げることは難しいです。
コロナ禍ほどでないにしろ、今後また業績が傾く可能性もみて検討しましょう。
3.全員のベースアップにこだわらないのであれば、頑張った数人だけ「昇任」させて手当を付ける方法もありますね。
こんな感じの答えでしょうか。
もちろん、実際には数字のシミュレーションも入れることが多いです。
でも、会社の業績が良くなると従業員全員の給料を上げたくなる経営者の気持ちは非常によく分かりますし、応援してあげたくなります。
でも、ベースアップは会社の続く限り一生もの、決算賞与は瞬間のもの、この違いを将来を踏まえて経営者さんにお伝えし、検討してもらうようにしています。
あくまで、上記は一例ですけどね。
まとめ



なるほど、佐々木先生の事務所の考え方がよく分かりました。
会社の様々な場面で、先生は「経営者」寄りの考え方をする、ということですね。
当事務所の目線は「経営者」目線ですね。
社会貢献意識が強い人、従業員を大切に思う人、利益第一主義の人、合理化の鬼の人…
いろいろな経営者さんがいますが、当事務所はとにかく「経営者さんの生活、人生が成り立つ」ことをベースにサポートしています。
なお、「遥か先に向かう」というモットーの出だしは「経営者人生が20年、30年」と続くことを考え、その長い時間をずっとサポートする、という意味を込めています。
ということで、当事務所のモットーの紹介でした。
もっと相談して、いろいろ聞いてみたいという方は気軽にお問合せどうぞ。