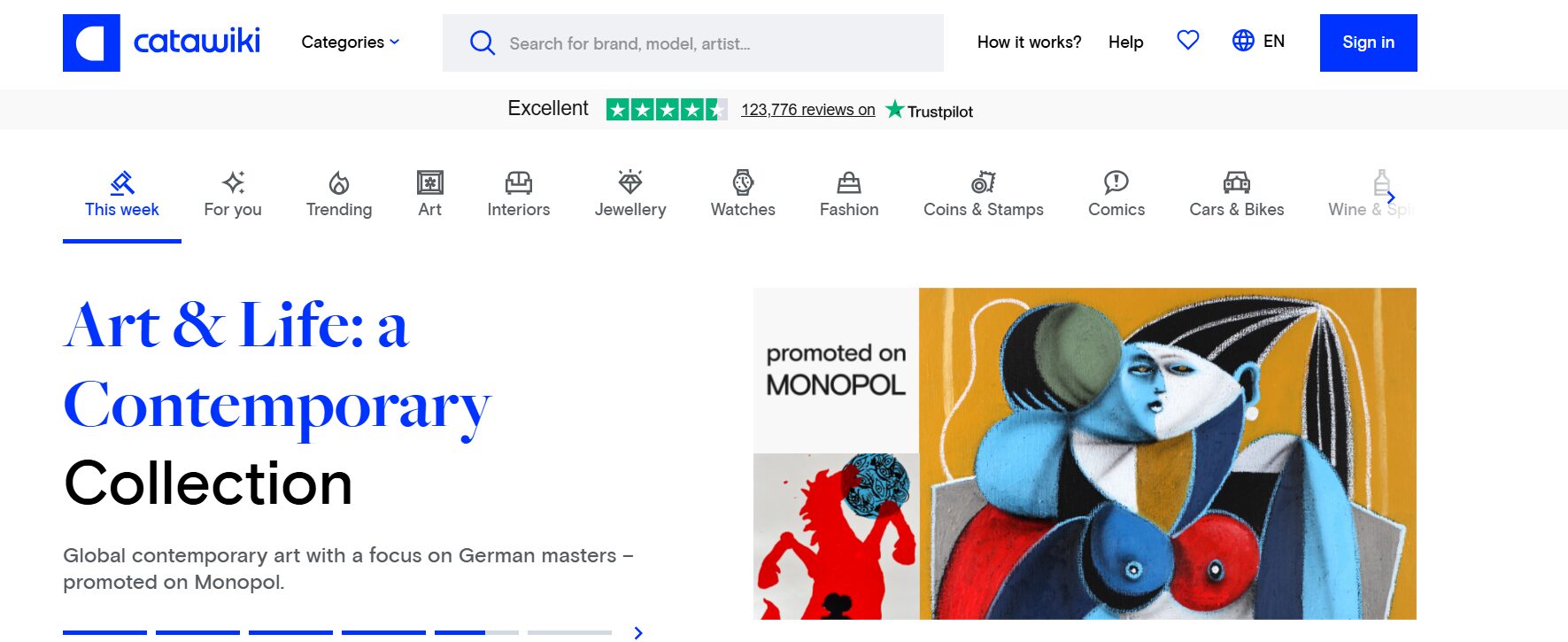※この記事は令和7年3月現在の法令に基づいて作成しています。
こんにちは、新潟市で活動しているハル税理士事務所、税理士の佐々木です。
今回も相続財産のうち、非課税となる財産についての解説です。
非課税となる財産の「生命保険金(死亡保険金)」について解説します。
なお、過去の相続の記事、関連記事はコチラ。

死亡退職金の概要
 2代目(予定)
2代目(予定)将来のことを考えて、死亡退職金について教えてください!
いえ…変な気持ちはないですよ…。
2代目さんの気持ちは分かります。
社長さん本人からの要望であっても言葉は選ぶ必要のあるトピックです。
役員の死亡退職金は有効な節税手段ですが、節税のためだけにやるものではありません。
今回は、感情論はともかく、制度としての死亡退職金について解説します。
死亡退職金も保険金と並んで非課税枠があるために相続税の節税スキームとして有名です。
しかし、生命保険金ほどには有名ありません。
また、税理士にとっては知識として当然であっても、会社の社長は知らないことも多いです。
そして、税理士としてトピックに出すのが難しいです。
生命保険金と異なり「自分が死んだことなんて縁起悪いだろ!」と叱られることもありますから、社長さんとの関係性に注意してトピックにする必要があるものです。
税理士としての相続対策の優先順位としては、生命保険金の方が毎年の所得税の削減効果もあるためトピックにしやすいです。
とはいえ、当事務所のモットーは「社長さんの会社と社長さんの人生を長い目でサポートしていくこと」です。
代表税理士の私が、「多少恨まれようとも必要がある」と判断すればアドバイスします(TPOは考慮します)。
さて、前段は終わりにして、死亡退職金の解説をします。
①死亡退職金の非課税枠



少し生々しいですが…
死亡退職金の非課税枠はいくらありますか?
死亡退職金の非課税枠から解説しましょう。
500万円 × 法定相続人の数
つまり、相続人が妻、子供2人の合計3人の場合には、500万円 × 3人 = 1,500万円 が非課税枠となります。
なお、この非課税枠は相続放棄の影響を受けません。
したがって、法定相続人の一人が相続放棄したとしても、非課税枠に影響はありません。
【備考】
死亡退職金が相続財産とされるのは、退職金自体が生前の労務の対価としての性質があるからです。
相続財産は、本来は「死亡時に被相続人が保有している財産」です。
しかし、死亡退職金は「死亡時に保有していません」。
死亡退職金が有効になるのは「被相続人が死亡し、会社の株主総会などで被相続人への死亡退職金の受給が決定」して初めて財産となります。
それにも関わらず死亡時の財産とみなされるのは、死亡退職金が生前の会社への貢献の成果だからです。
②死亡退職金の注意点



なるほど、相続人一人あたり500万円が非課税。
けっこう大きなメリットですね。
上記のとおり、死亡退職金には非課税枠があり、500万円×相続人の数というメリットがあります。
また、相続放棄の影響も受けませんので、配偶者と子供の人数分の非課税枠があり、相続税率によっては1,000万円レベルの節税効果があります。
しかし、実際の運用にあたっては、次の点に注意する必要があります。
(ⅰ)死亡後3年以内に確定していること
死亡退職金の金額の確定時期について注意が必要です。
あくまで、死亡退職金は被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産とみなされて相続税の課税の対象となります。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税対象となります。
国税庁 タックスアンサー No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
つまり、何らかの理由で被相続人の死亡後3年を超えて確定したものは、その受取人の「一時所得」となります。
一時所得も所得税法上で優遇のある所得ですが、相続財産のように非課税枠はありません。
したがって、死亡退職金については社内規定により「受取人」「退職金の計算方法」について、定めておく方が税務調査での否認リスクが減ります。
(ⅱ)死亡退職金の受取人
死亡退職金は保険金と同じく、本来は相続財産ではありません(死亡時に有していないため)。
みなし相続財産であり、民法上は受取人の固有財産であすが、相続税法上は相続財産とみなされるものです。
そして、相続財産として非課税枠の適用を受けるためには、法定相続人が受け取る必要があります。
法定相続人以外の第三者が受け取った場合には非課税枠の適用はありません。
とくに、「遺贈」として法定相続人以外の人や本来の受取人以外の人が受け取る場合には、相続税法上、細かな配慮(代償債務の支払いなのか、など)が必要となります。
この点、受取人については、その効果を考えて設定する必要があります。
契約税理士によく相談するようにした方がいいでしょう。
(ⅲ)弔慰金と混同しない
被相続人の死亡に際して、勤務していた会社から弔慰金(ちょういきん)が送られることがあります。
これは、死亡退職金とは扱いが異なるものです。
弔慰金は被相続人を弔い、遺族を慰める意味で送られる金品のことを言います。
香典とも異なるものです。
簡単にそれぞれの特徴を覚えておきましょう。
- 死亡退職金:会社における勤務への功労に対する一時金。退職金規定や株主総会での決定に基づき支給される。
- 弔慰金:故人の功労に報いるための金品。福利厚生制度に基づき支給される。
- 香典:葬儀の参列者が喪主に渡し、霊前に供える金品。
なお、弔慰金にも非課税枠があります。
簡単に記載しておきますので、参考までにどうぞ。
- 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額 - 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額
節税目的のトピックとなりますが、きっちりと福利厚生として弔慰金の制度を明文化することで、非課税範囲を拡大することは可能です。
ただし、創業者の利益目的でやるものではありません。
従業員を含め、社内全員の福利厚生制度として行う必要があります。
(ⅳ)会社側の処理
生命保険金と異なり、死亡退職金の場合には必ず会社が支払主体となります。
したがって、会社側の経理処理、つまり損金計上(法人税法上の経費)となる限界についても知っておく必要があります。
死亡退職金は生前退職金と同様に「功績倍率法」を利用することが一般的です。
功績倍率法は複数ありますが、実務で採用できる「最終功績倍率法」は次の計算式によります。
最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
(例)最終報酬月額が50万円、役員在任年数が20年、代表取締役(功績倍率=3)の場合
50万円 × 20年 × 3 = 3,000万円
※ 上記はあくまで「一般的な限度額」を計るもので、確実に安全かどうかのラインではありません。
本人の会社への関与度、絶対的な金額、最終報酬月額の妥当性などでかなり変動します。
このケースだと、退職金は3,000万円が税務調査で争いがないであろうギリギリのラインとなります。
死亡時の役職や、役員在任期間によりかなり差が出ます。
死亡退職金の場合には、非課税枠も気にしつつ、会社側の損金算入限度額も気にする必要があるため、会社と個人の二つのものさしで考える必要があります。
税理士としての意見ですが「退職金」については、生前時でも死亡時でも「契約税理士に相談し、適用条件を確認してから行う」ことが重要だと思います。
③生前退職金と死亡退職金の違い



そういえば、生きているときにもらう退職金と死亡退職金で違いはあるんですか?
簡単に言うと、適用される法律が違います。
生前にもらえば「所得税」、死亡によりもらえば「相続税」が適用されます。
そして、その結果一番異なるところは、「源泉所得税の有無」と「所得税と相続税での税率」です。
生前退職金(所得税法)の控除額
生前退職金の場合は、次の算式による退職所得控除が働きます。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
国税庁 タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
この退職所得控除以内の退職金であれば、「退職所得の受給に関する申告」を会社に提出することで、税金関係は「0円」で完結します。
この退職所得控除を超える場合でも、「収入金額(源泉徴収前) - 退職所得控除額) × 1 / 2 」で算出された金額に速算表を当てはめれば源泉徴収額が出ます。
国税庁 タックスアンサー 別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表
この源泉徴収義務が会社側に発生することが大きな違いの一つですし、税率も異なります。
死亡退職金(相続税)の控除額
これは、前述のとおり、法定相続人の数 × 500万円 です。
そして、これを超えた額には、相続税での税率が掛けられて税額が出ます。
なお、死亡退職金に源泉徴収義務はありません。
したがって、支払う会社側は源泉徴収する必要はありません。
ただし、「退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)」を支払日の翌月15日までに管轄の税務署に提出する必要があります。
※ 死亡退職金が100万円以下の場合は省略できます。
なお、源泉徴収義務の有無は税金知識に強い人であれば、「結局、受け取る本人は後で(確定申告)で精算されるし、関係ないじゃない!?」と思うでしょう。
しかし、支払う会社の側にとっては、源泉徴収をしなかった場合には「源泉所得税」での法令違反となり、「不納付加算税」「延滞税」を課されるリスクがあります。
源泉徴収制度はもらう側より、支払う側に厳しい制度なのです…。
そして、もちろん税率も相続税と所得税で違います。
相続税では控除額が「法定相続人の数 × 500万円」と大きく取られている反面、1/2することはありません。
そういった点も異なる点です。
(一概に生前、死亡後でどちらが有利と言い切れるものではありませんし、また税額だけを考えてするものではありません。
大切なのは、退職される方と家族の人生です。)
まとめ



かなり、難しいですね…。
退職金って、こんなに制度がこんがらがっているんですね…。
弔慰金や香典も絡むんですね。
死亡退職金、というか退職金全般がけっこう税務上難しいです。
「最終功績倍率法」が税理士業界では有名ですが、それにはまらないケースもあります。
特に、2020年代の前半にコロナ禍で社長、会長の報酬を大幅に減額した場合には「最終報酬月額」の適用は実態を表しません。
その場合には、「平均報酬月額」などの他の方法が求められますが、かなり繊細な内容となります。



ふむ…。
我が社もコロナ禍の影響はあったな。
私の報酬も最盛期に比べれば、いろいろな意味で抑えているが…。
佐々木さん、これはマイナスに働くのかね?
確実にそうとも言えません。
退職金の金額には、そもそも「税法上、決まった額は存在しない」という大前提があります。
そのうえで、世間一般から見て、過去の裁判例も踏まえ、無理のない金額を合理的に定める必要があります。
難しい面が多い「死亡退職金」ですが、このようなグレーな部分こそ税理士を頼ってください。
さらに深く相談したい方は、気軽にご相談ください。